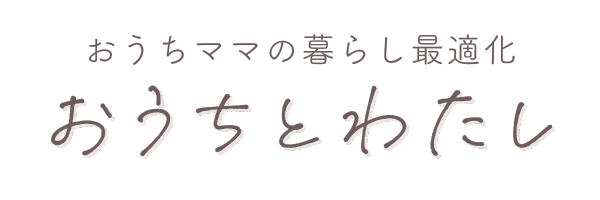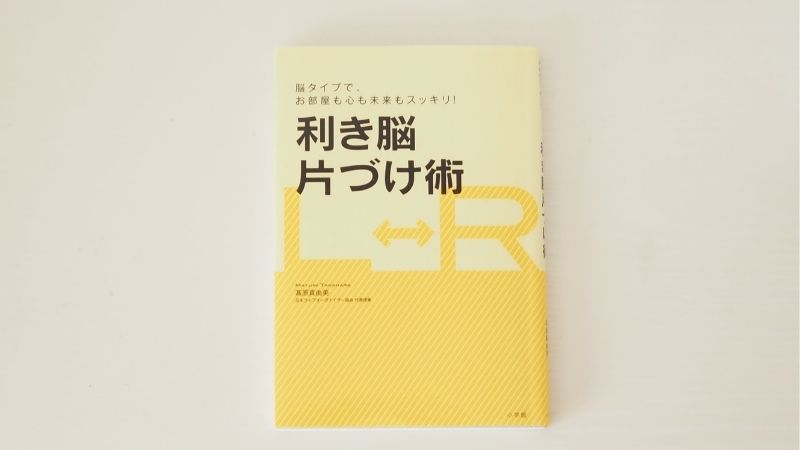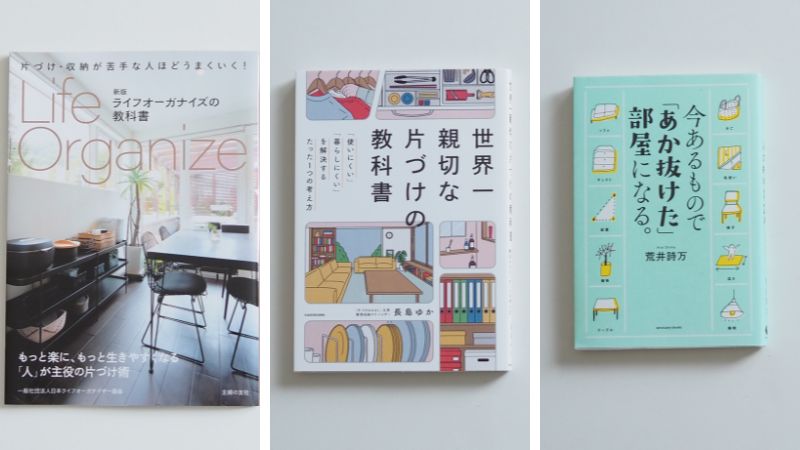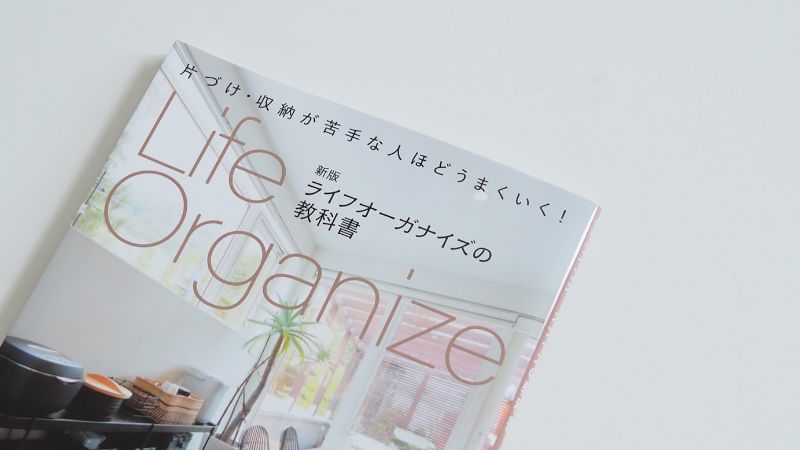片づけやすさは親子でも違う | 私と小1息子の文具収納の違い実例

ライフオーガナイズを学んだときにびっくりしたことのひとつが、「親子でも片づけやすい方法が違う」ということ。
親が教えたり整えたりしても、子どもにとって片づけにくい方法だとうまく片づけられません。
子どもに片づけをしてほしいと思ったら、子どもが片づけやすい方法を見つけて整えるのが大切です◎
この記事では片づけやすい方法が違う、私と小1息子の収納実例を紹介します。
同じ文具収納でも、親子で片づけやすい収納の仕方が全然違いました!
子どもがスムーズに動けるようになる収納づくりの参考になれがうれしいです^^
人によって片づけやすい方法は違う


片づけは人によってやりやすい方法が違います。
たとえば服のしまい方
「たたんでしまう」のがラクな人もいれば、「ハンガーにかけてしまう」のがラクな人もいます。
私の体験談
以前、SNSで見て「白い収納ボックス」を使っていました。
けれど片づけにくくて、物を置きっぱなしにしがちに…。
私の場合、「収納ボックスは中身が見えるもの」があっていると判明◎
収納アイテムを変えただけでも、片づけがラクになりました。
そして、ひとつ屋根の下で暮らす家族や親子でも片づけやすい方法が違ってきます。
親が収納を整えても、子どもにとって片づけにくい方法だと、子どもが片づけてくれないという状態に…。
親子で片づけやすい方法が同じとは限りません。
子どもの収納は、子ども主体で考えるのがおすすめです。
【実例】私と小1息子の文具収納の違い
ここでは私と小1息子の収納の違いの実例として、
- 私の「立てる収納」
- 小1息子の「置く収納」
を紹介します。
親の私は「立てる収納」


私の文具収納は、「立てる」収納ケースを使っています。
仕事をするときは開いて設置し、使うものを出し入れしています。
使い終わったらパッとしまえて、机にペンが散らかることがなくなりました。
開け閉めも必要ないので、使い終わったらサッと片づけられるのもお気に入りポイントです。
私が使っている収納ケースはこちらの記事で紹介しています。
小1息子は「置く収納」


小1息子の文具収納。
浅くて底が広めなので、「使いたい物を上からパッと取り出せる」のが使いやすいようです。
使い終わったあとも、片手で一気に片づけられるので、置きっぱなしもグッと減りました^^
利き脳で片づけやすさのヒントが見つかる
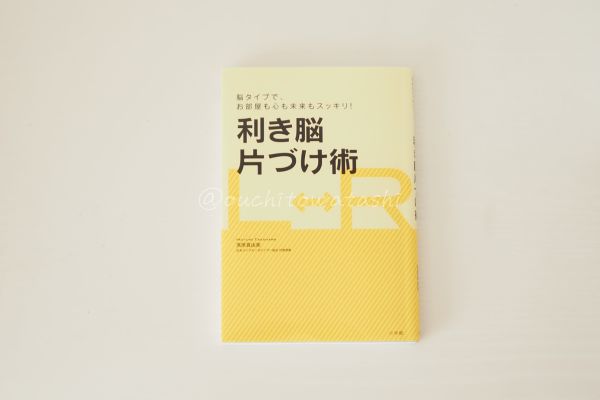
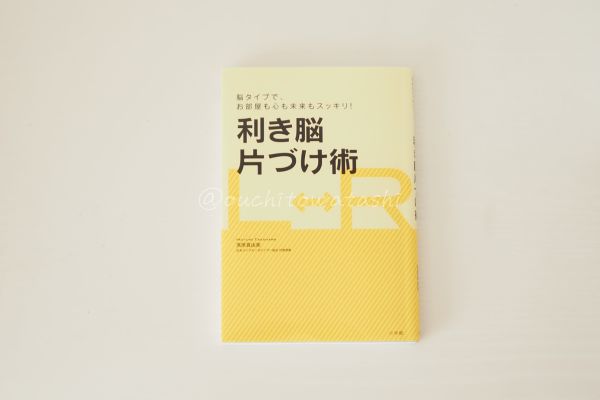
ライフオーガナイズの片づけでは、片づけやすい方法を見つけるヒントとして「利き脳」を取り入れています。
利き脳片づけは、右脳タイプ・左脳タイプによって得意なことが違い、それを片づけに活かそうという考え方です。
収納も、白いボックスにラベリングではなく、「半透明の収納ボックスで中身を把握する」方法があっています^^
利き脳のタイプによって片づけやすい方法や使いやすい収納アイテムが変わってきます。
手軽にチェックできるので、ぜひためしてみてください◎
おわりに
収納方法はひとつではないし、その人の行動パターンによっても片づけやすさは変わってきます。
家族でも親子でも片づけやすい方法が違うので、その人にあわせたやり方を見つけてみてください◎
片づけやすさが見つかる1冊
\暮らしを整える片づけ本/
ライフオーガナイズをくわしく知る1冊◎
収納・配置の仕組みで暮らし整える◎
センスに頼らない空間づくりに活用^^