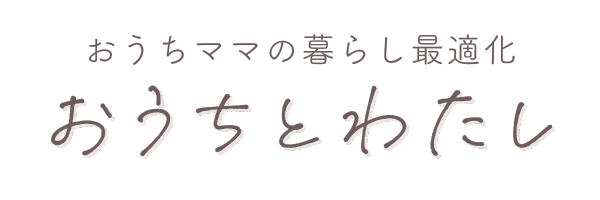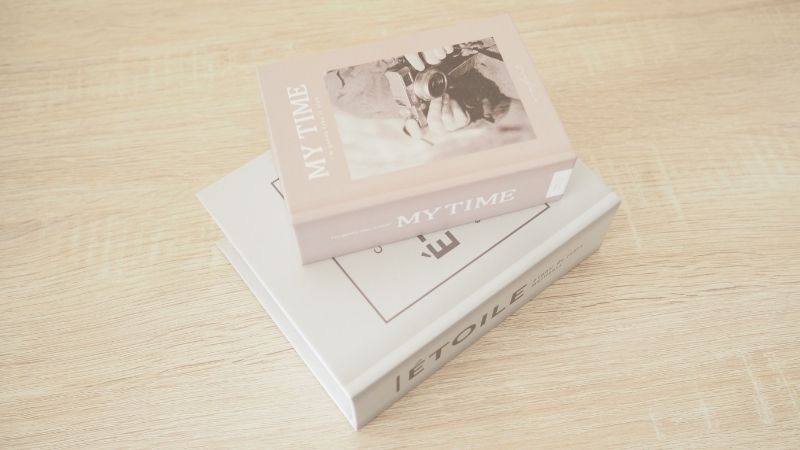ちょうどいい物の量チェック | 適量より多いときのサイン3つ

物の量がちょうどいいと、暮らしを快適に、毎日がスムーズに回るようになります。
けれどちょうどいい物の量を見極めるのって難しいですよね。
この記事では暮らしにちょうどいい量を見つけるポイントのひとつとして、物が適量より多い3つのサインを紹介します。
物の個数ではない、自分サイズの「ちょうどいい」の見つけ方をぜひ参考にしてみてください◎
物を手放すコツはこちらの記事で解説しています。
物の適量は人によって変わる

暮らしを送るうえでちょうどいい量は人によって変わります。
端から見れば「多すぎじゃない?」と思う物でも、本人にとってはちょうどいいこともよるあることです。
たとえば、我が家で多く持っているアイテムのひとつが菜箸。

10膳近くあるのですが、人によっては「1膳で十分」という方もいると思います。
けれど副菜を作り置きすることがある我が家ではこのくらいが「ちょうどいい量」。
まとめて作ってからまとめて洗うのがラクでちょうどいいのです◎
このようにライフスタイルによってちょうどいい量は変わります。
適量は誰かと比べるものではないし、誰かのマネをしても暮らしが快適になるとは限らないので注意が必要です。
物が適量より多いときのサイン
ここでは物が適量より多いときのサイン、
を解説します。
どれを使うか悩む

物が多いと、物を選ぶときに
- 「今日はどの服を着ようかな」
- 「どのペンを使おうかな」
と迷ったり悩んだり、選ぶことが負担になってしまいます。
日々は選択と決断の繰り返し。
私たちは1日に9,000回の選択・決断を行っていると言われています。
物が多い=選択肢が多いというのは、脳が疲れてしまう原因のひとつです。
私は以前、「服はたくさん持っていたら安心」と思い込んで、様々な服を所有していたときがありました。
けれど実際は毎朝「何を着ようかな」と迷いすぎて
- 服はあるのに着る物がない
- 結局いつも同じ服を着ている
という状態に。
選ぶだけで疲れて、結局同じような服しか着なかったんですよね。
そこから骨格診断・パーソナルカラー診断を受けて、「似合う服」を基準に服を4割ほど処分することに成功。
服の全体数は減りましたが何を選んでもしっくりくるようになり、毎日の服選びに迷わなくなりました。
どれを使おうか選ぶことに疲れを感じるときは、物の量を見直すサインです。
スムーズに出し入れできない

引き出しを開けたとき、パッと見てどこに物があるか把握できないということはありませんか?
このように物を使うときにスムーズに出し入れできない場合、しまっている物が多すぎるかもしれません。
部屋全体の物の量が多くなく見えても、
- 1か所に詰め込みすぎていつも探し物をしている
- 押し入れやクローゼットの奥にしまったはずだけど見つからない
ということが多い場合は、その収納スペースに入っている物が適量以上だと考えられます。
我が家で量を見直したのがシンク下収納。
「なるべくたくさんしまうこと」を意識しすぎて、シンク下収納が使いづらくなってしまったことがありました。
ボウルを取り出すたびに棚板に引っかかったり、他の物をよける必要があったり、毎日のごはん作りのモヤモヤポイントに。
「物をたくさんしまう収納」ではなく「物を出し入れしやすい収納」を目指したら、立ったままスムーズに出し入れできるようになりました。

物の量の指標として「7割収納」がいいと言われているとおり、物を出し入れすることを考えると7割くらいがちょうどいいと感じています。
物を使うときに探すことが多い、出し入れが大変だと感じるときは、7割収納を目指すのがおすすめです。
管理が大変だと感じる

物を持つというとこは、維持管理のコストもかかるということ。
物は所有するだけではなく、
- 収納するスペース
- 長く使うためのメンテナンスする時間やお金
などのコストがかかります。
このような維持管理にかかるコストが負担だと感じるときは、所有する物を減らすのがおすすめです。
必要な物だけど維持管理の大変さを減らしたいという思いから活用しているのがレンタル用品。
我が家の場合、子どもの学習用のスキーは毎年レンタルしています。

レンタルすることでオフシーズンの保管やメンテナンスの必要がなくなったので、負担を減らすことができました。
毎年ぴったりサイズを借りられるのもメリットです◎
使用頻度によっては所有ではなくレンタルで十分の物もあるので、ぜひ選択肢のひとつに入れてみてください。
整理は捨てるではなく「選ぶ」

「物が多いから減らそう」と思ったとき、「何を捨てようか」を考える方も多いと思います。
けれど捨てる物を探しても、なんとなく必要そうだったり、まだ状態がいいからとなかなか手放せません。
そんなときにおすすめなのが「暮らしにとって必要な物・大切な物を選ぶ」という考え方。
自分にとって最適な暮らしを考え、その中で必要な物を選ぶことで、物を手放すハードルがグッと下がりますよ◎
「捨てるから始めない」物の整理はこちらで詳しく解説しています。
おわりに
ちょうどいい物の量はライフスタイルによっても変わってきますし、人それぞれ違います。
暮らしを最適化するためには周りの平均ではなく、自分自身の暮らしと向き合って適量を見つけるのが大切です。
ぜひあなただけの「ちょうどいい量」をさがしてみてください◎